サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
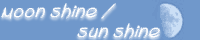
家族編第3話
陽に言われて数時間後。私が用意した夕飯を二人で囲む中、ためらいながら母親に相談してみた。回答は、以下。
「李花が会いたくないって言うなら、ドタキャンしたってかまわないわ。ただ私はあった方がいいと思っている。大学生になってまで、引きずりたくはないでしょ?」
そういわれると、どっちに転んだらいいんだろう。――と悩んでしまう。
決めるのは自分、そう委ねられてしまうと、誰にも甘えることが許されないようで、緊張する。
夢――というか、なりたい職業を決めたのは、中三の時。お母さんが私にどんな夢を思いはせていたのかは知らないけれど、きっと私の夢と同じではなかっただろう。そもそもなかった可能性もある。
ただ一方で、父親に望まれた音楽の道を進む弟がいる。はじめた幼少の頃から彼は、この緊張と戦っていたんだろう。父は彼を支えたかったのか、彼の親権を望んだ。
親権がどうやって決められたのか、詳しいいきさつを話してくれたことは一度もない。だからいつも、想像ばかりが頭を占める。――私は父にとって、いらなかった存在なのだと。音楽を選ばなかったから。
でも母は、その答えはくれない。私と父の問題だからといって、あいまいにしか答えない。今だって、委ねることによってあいまいにする。
夢を決めたとき、引きずらないって決心した。自分で選んだことに誇りを持つと、母も言ってくれた。でも、思考のループが止まらない。
「引きずりたくないけど、引きずらずにはいられない。だっていつも、お母さんは答えをくれないじゃない」
「私が何もかも話して、私の答えに、それで満足できるの? それで本当に、過去のことを引きずらずにあなたは前を向いて生きていけるの?」
そんな確信、あるわけがない。
「それにあなたがほしいのは、私の言葉ではないでしょう?」
さすが母親だ。一気に核心だ。
母は、夢を決めた時から、私に口出しすることをやめた。きっとそれからなのだ。父が急に、心を占め始めた。楓を思い出せば父も思い出し、陽と楓のことを話せば、父も何とはなしに話になったりもした。
だから、――思い出してしまう。父の広い背中。節くれだった手と、それにつながれた幼い手。どうしてあの手が自分を引っ張ってくれないのだろうと母に問いかけ、教えられた現実。弱った身体が、追いかけることさえも許してくれなかった、雪の日。
幸せな幼少期の終わり。不幸ではない、でも何かが欠け続けた私の始まり。
思い出せば、ぐるぐると、完結するあてのない、言葉にしても楽にならない感情があふれる。泣いてすっきりしても、それは完結ではなく、ましてや解決でなんてありえない。
「あって話して、それが一番の解決方法だと思うわ」
「……あったって、無駄だよ」
今聞く「理由」なんて、あの頃のいいわけじゃないか。
それに、どういう顔をしたらいいんだろう? 子供のころからの夢をかなえようと、いろいろなことを成功させている楓と、受験をはじめ失敗ばかりの自分じゃ、比べるまでもなく自分が劣等生だ。何度だって同じことで悩んで、うじうじしているのだって抜け出せそうにない。
何度だって思い出してしまうのだ。あの背中。つながれた手。追いかけることが出来なかったことを、それを幸せだったんじゃないかとさえ思うときもある。追って、振り払われる可能性だってあった。だって、――音楽が出来なければ、あの人には――
「じゃぁいつ?」
「わからない。答えも解決も、感動の再会も、私にはいらない。お母さん一人で、行って」
「李花、あなたも家族の一人なのよ?」
「その家族を壊したのはどっちなのよ!!」
「楓やお父さんと一緒に過ごして、それなりに暮らしていたのを、お母さんが壊したんじゃない! お父さんに愛想つかして、離婚して、親権ばらばらにして! どうして? どうして、私達にしわ寄せを作るの……?」
「じゃぁ、私が苦しめばよかったの? 一人に苦しみを与え続けるのが、家族だって言うの?」
「そんなこと言ってない」
わかってる。八つ当たりだって。
リビングを抜け出し、自分の部屋で一人泣く。
どうして殻にこもってしまうんだろう。どうして向き合えないんだろう。
誰かが悪いんじゃない。誰が悪いのかなんてわかりきってる。
やるべきことも、やれることも、理性の区別はついてる。追いつけないのは、感情。
時間は待ってはくれない。入学式だって憂鬱だ。第一志望じゃないのに。
行きたいと思ったことなんてなかったのに。
入学式当日が、来た。式自体は午後からで、お母さんは仕事だから一人で会場に向かう。電車の中でも、昼食を食べているときも、迷いが生まれる。少し自分を甘くすれば家に帰りそうな心境の中、あふれそうになる涙をこらえて急行に乗り、路線を乗り換える。
どんな顔しているかなんてもうわかんない。ただ、吐き気をこらえて、入学式の終了後、都内のホテル、ロビーへ向かった。母だけしかいなくて、私の姿を見ると、気丈な母が、少し目をにじませた。
それから三十分と待たないうちに、楓とお父さんが、揃って来た。
何年かぶりに一メートル未満の距離で楓にあう。背は高くて、男の子になっている感じ。お父さんのほうを見ると、なんだか顔は青ざめていて、とても威厳なんかとはかけ離れていた。
記憶にある唯一の姿は、置いていく後姿だったから。こんな顔だった、こんな声だったなんて、比較対象物がない。お母さんはもうすでにけろりとしていて、顔色一つ変えずに話している。おとうさんが小人のように背中をまるめ、びくびくしながら、エレベーターに向かう。昔からこんなもんだったんだろうか。
須王と並んで両親の後姿を追いながら歩く。
二人が並んだ後姿には、記憶が符合する。でも、父親はこんなにもよわっちょろくて、恐怖なんかとは別次元にいたんだろうか? こんなにも小さくなってしまわれると、どうにもこうにも憎めない。
ふと足を止めると、楓が手を出してきた。どんな意図だったのかはわからないけど、ためらわずに握ってみて、なんだか急に恥ずかしくなる。父の隣で母が年甲斐もなくウィンクなんてして見せた。
口元が、頬が、目元が。自然と、ほころんでいく。
それは、ある日の夕食のこと。
二人の大学入学祝いにと、両親がレストランのディナーを予約していた。久しぶりのシェフの料理に舌鼓を打ちながら、たわいもない話に花を咲かせる。共通の友人である西尾家は、格好の話の種。ほんとうに、ほんとうに他愛もない話ばかりだった。
幼い頃にした遊び。失敗談。教訓。エトセトラ。
時間を埋めるように、中学時代の話をしたりもした。これからの進路も。
「李花、お父さんたちにあえてよかった?」
「――まあまあ」
別れ際、二人の前で、お母さんが私に聞いた。
夜は十時を越えていて、お酒も飲んでいないのにほろ酔い気分だった。見上げた孤高の満月に、わけもなく涙があふれた。懸命にこらえて、最後、お父さんと楓、二人と携帯のアドレスを交換したりした。
大学に入学して一週間近く。どたばたする生活の中、夜になればひっきりなしで父からメールが届く。楓にメールを送っても、帰ってくるのは二言三言。わが弟ながら、そっけないと思う。
ただそんなたわいもないことが、うれしくてしかたがない。
青木李花、大学一年の春。ある日突然、前触れなく、我が「家族」は動き出したのだ。
サイトトップ>『moon shine / sun shine』目次>家族編第3話