サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
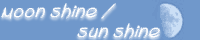
姉弟編第12話
ヴァイオリンを始めたのは、父親の影響が強い。続けられたのも、結局のところ父親に操られている気がしなくもない。――結局のところ、自分も父親もヴァイオリンバカなのだと思う。光のピアノバカをもしのぐかもしれない。
言わせる人に言わせればヴァイオリンはいわくつきだと言う。たしかに、父親は息子のヴァイオリンのレッスン料やら他経費で母親と言い争い、離婚したし、そこには俺がヴァイオリンをやっていたことにある。
離婚したばかりのころは、ヴァイオリンを見るのさえもいやになったが、今ではヴァイオリンがなければ生きていけないとさえ思ってしまう。魅せられているのか、取り憑かれているのか。決めかねるが、どちらも本望だ。
舞台で名前を呼ばれる瞬間が緊張の絶頂だ。一礼して、楽器を構えてしまうと、緊張は楽器がすべて吸い取っていく。ヴァイオリンをあごで押さえて、弓を構える。陽に合図を送ると、いっせいに音を弾く。
高校の音楽科の、同じヴァイオリン専攻に、弾いているときに何を考えているのかと聞かれたことがあるが、何も考えていない。次はG線、なんてことさえも考えていない。このとき、取り憑かれていると思う。
終わるのだってあっという間に終わってしまう。そのときになってだんだん、人間の自分が戻ってくるのだ。たとえばミスをするならこの瞬間だ。一瞬の隙が生む。
一生憑かれたままでいたい、と幼馴染に言うと、私の愚痴は誰に言えばいいんだとしかられたこともある。
終わって人間に戻る。喝采。歓声。―― 一礼しても、途絶えない。開放感の中で、二階席を見ると、ヴァイオリンを持つ手が緩んだ。陽の靴の音がコツコツと響いて、意識を取り戻す。陽と大樹さんが言っていた理由が理解できた。
両親が離婚したときは、五才の子供だった。それでも覚えている。――忘れるわけがない、家族の顔。
振り返って、してやったりと微笑む陽に、不覚にもまぶたが熱くなってきた。袖から、精一杯見ようとすると、人影が動いていくのが見える。記憶よりも成長した人影が、コートを脇に出て行ってしまう。
拍手はとまらない。定期演奏会にアンコールを求めるな、と舌打ちしたくなってしまう。ヴァイオリンをケースにおさめ、憧れの人をじっと見つめた。陽は驚いたようにその様子を見つめて、父親のほうに目配せをした。
「行き給え、青年。うちの少年が先手を打っているかもしれないが、目くじらは立てないでくれ」
大樹さんが言ったのを聞いてから、陽と二人、辺りに光がいないのに気づいた。二人して接点が見つからずに首を傾げるが、スタッフがこちらに目線を向けて、無言の訴えをする。ヴァイオリンケースを大樹さんに渡して、一礼。
「行ってらっしゃい、須王」
陽が楽譜に視線を流して言う。その肩を軽くたたいて、スタッフから傘を借りた。ホールには、かすかな雨音が音楽を作っていた。
「……アンコールで初見って、ありえなくない??」
「なに、私もこんなに緊張して弾くのは初めてだよ」
楽しそうに微笑みながらヴァイオリンを手にする父親を見て、娘は嘘付け、とつぶやいた。陽は演奏会などとはまったく関係のないところで大きくため息をつくと、同時に力も抜けていった。
「あーぁ、私また光ににらまれそう。お父さんもわかってるでしょう?」
大樹はなにごともなかったかのように振舞い、舞台に入ろうとし、足を止めて振り返った。それは、演奏家の顔と父親の顔を、たして二で割った表情。
「うちの息子と、須王くんを走らせているのはどんな子なんだ?」
「……知ってるくせに」
彼は彼の子供を愛し、信頼しているのだから。
サイトトップ>『moon shine / sun shine』目次>姉弟編第12話