サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
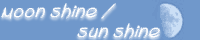
姉弟編第11話
舞台発表前でも、飄々としているのが西尾陽――俺の幼馴染である。それはいつまで経っても同じことで、どんな意味合いの発表会でも変わりはない。
「これが最後だなんてねぇ」
練習中、そんな彼女がポツリとつぶやいたのはいつだったのか、記憶はない。ただひどく驚いて、でも当たり前のこと、自然なこととして、受け入れられた。そもそも、高三のこの時期の演奏会に出ること事態が非常識なのかもしれない。
控え室で調弦している俺の隣で、鼻歌で調子をそろえる。カリカリした雰囲気はなく、単語カードをぱらぱらとめくる受験生。
「よくやってられるな」
「心の持ちようじゃない? まぁ、ピアノが主旋律って曲じゃないから、そんなに責任重大でもないし〜?」
「やめてくれ、お前がミスしたらこっちが狂う」
「私を信用してないって言うの?」
そういわれると、自然に笑みがこぼれてしまう。十年来の付き合いで、そう来るか。緩んだ頬を引き締めて、ヴァイオリンを肩から下ろした。陽が立ち上がり、誘導係がドアをたたく。なんとなく差し伸べられた手を握ると、幼いころを思い出した。
自慢じゃないが、俺の両親は俺を理由に離婚した。もともと不仲だったのか、とか、他の素因を知らない。だから親戚のなかはあうたびに、この子供が悪い、とあからさまな視線を送るものもいる。子供の時分からそんなんだったので、悪意のある人間のそれには慣れていた。いやな子供だ。
舞台は視線が好意的な分、拍手と歓声が心地よく感じられる。ヴァイオリンがそこにあって、それを弾ける自分である限り、幸せに大差はないかもしれないが。まったく知らない誰かが、ただ曲に対してだけ送る喝采は、得がたいものだと思う。
舞台袖で、西尾光の演奏を聴く。スランプだったのか、ここ数年弾いていなかったという指はマメで硬くなっている。本来ならばピアニストにあるまじき行為だと思うが、がむしゃらにしかできないやつにはお似合いだと俺はひそかに思っている。
俺の憧れのヴァイオリニスト西尾大樹の子供である西尾光が弾く曲は、ベートーヴェンの『月光』をアレンジしたもの。実はヴァイオリン用におこされた楽譜もある。さすが大樹さんの曲はすばらしい。弾きこなす光の技量もいいが。
その光の双子の姉が、傍らにいる西尾陽だ。現役大学受験生。有名進学校に通う、どうして今この場にいるのか不思議な女は、彼女以外にはいないだろう。
「須王、顔に何もついてないなら、私の顔凝視したって緊張はとけないわよ?」
――この憎らしいほどよく回る口も、弟関係になると愚痴の嵐になる。正直弟への愚痴は本人にこぼすものだと思っているが、この女の中で俺がそういうポジショニングなのか、愚痴はこっちに垂れ流しだ。納得できない話だ。極度のブラコン、という付加情報も忘れられない。
「……そうそう、二階席の中央かな? 須王のファンが座ってるから」
「はぁ?」
「もう、チケット頼まれてねー。でもあんまり顔は見せたくないって言うか、二階席? みたいな」
「見ねぇぞ俺は」
「恥ずかしがっちゃってぇ〜」
ほんのりナチュラルメイク、めかしこんでいてもふざけた女の仮面がはがれることはないらしい。舞台に響かない程度の小声の会話でも、会話のレベルは下世話なおばさんの井戸端会議。――なのはこの女だけだと思いたい。
「須王くん、陽」
ここ数日のレッスンで聞きなれた声が、自分の名前を呼ぶ。ああ、至福の瞬間だ。
「お父さん? どうしたの、舞台袖まで」
「いやぁ、楽しそうだと思ってね」
「……須王くん?」
「昇天してるから、須王」
呆れたように陽が言う。そういわれても、何度呼ばれても、憧れの御方が目の前にいれば感無量、自分の名前を呼ばれたら昇天したくもなる。観客の半数以上は今光が弾いている――西尾大樹作曲の曲を聞きたくて来るほどの、大作曲家だぞ。
家族ってうらやましい。
「須王くん、二階席のほうは見たかね?」
「陽と同じことを言いますね。ここからじゃ見れませんよ」
「是非見るといい。いや、見なければいけないな。なに、若いんだから何かあったら突っ走るといい」
「はぁ……」
せっかくの言葉も、意味がわからなければ感激の仕様がない。そうこうしているうちに、光の曲が終わり、拍手がホールを包む。顔を赤くした光が戻って、父親の姿に驚くが、感極まったらしく、頬に幾筋もの涙を流す。
なぐさめる父と子の姿を後ろ目に、俺と陽は舞台に入っていく。
サイトトップ>『moon shine / sun shine』目次>姉弟編第11話