サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
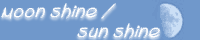
双子編第8話
「初めてヴァイオリンの演奏を聞いたのは、父親の知り合いのコンサートだった。あこがれてやり始めたヴァイオリンは、その人のような澄んだ音を出すのが難しくて、何度も投げ出したくなった。
毎日何時間も練習して、小さな曲が弾けるようになったとき、真っ先に父親に聞かせた。父親は喜んで、調弦に必要な音感を養った方がいいな、といって、ピアノにも通わせるようになった。
父親は音楽の道で挫折した人だから、息子の俺に期待していたんだ。けれどそれは母親の意見とは違っていて、――俺が一ヶ月、また一ヶ月とヴァイオリンを続ける度に、母親の笑顔を見せる回数は減っていって、両親は離婚した。
子供心にヴァイオリンを続けることに無意味さを感じた。夢にひたむきな子供ではいられなくなった。金という現実が引き起こした親の別れは、五歳の俺には強烈過ぎた。どうして辞めなかったんだろうと、泣きながら、ヴァイオリンも弾かずにすごした。一ヶ月、ぐらい。
見かねた父親が、ある日、一人の男の人と、小さな女の子をつれてきた。男の人は憧れのあのヴァイオリニストで、女の子はその子供の、社交的なほうだった。教室に通っていた頃によく遊んでいた子だったから、少し、驚いた」
須王は苦笑いを浮かべた。光はなんとなくむっとして、どうせ社交的じゃない、と枕に顔を押し付けた。耳をふさがずに。
「男の人は近くでヴァイオリンを弾いてくれたけど、頑なになった子供心はなかなか解けなかった。意固地に、ヴァイオリンを弾かなくなれば、母親が戻ってくると思っていたんだ。母親は、俺にあうのを拒絶していた。ノイローゼだったんだろう。
男の人は無理せずに、毎日ヴァイオリンを弾きにきて、かえっていった。女の子は父親と一緒に来て、一緒に聞いて、一緒に寝た。
ある日女の子は、目ざとく俺の部屋の片隅に置かれた子供用のヴァイオリンを見つけて、俺に弾けと命令した。拒んだ俺に、じゃぁ、といって弾いた女の子のヴァイオリンは、とても聞けたもんじゃなかった。耳にとって不快な音を嫌って、弾かないでと言っても、女の子は止めない。仕方なくヴァイオリンをひったくると、久しぶりに持ったヴァイオリンに、腕が震えた。
女の子が持っている弦を受け取ると、一番最初に弾いたのは、男の人がよく弾いていた、いつも聞いている曲だった。たどたどしい演奏でも、女の子は喜んで。
自分の音で弾いた曲で、喜んでくれる人がいる。そう気づいたときに、一番最初に喜んでくれた父を思い出した。
夢を託された自分があって、夢を強制されたものと認識していない自分があって、目標となる人がいる。その時俺は自分を知ったんだ。
ヴァイオリニストになる夢を、あきらめられるわけがない」
枕に顔を伏せたまま、耳に届くしっかりとした声。似たような声を以前聞かなかったか。そう、震える肩で、気丈に胸を張っていた彼女の声と似ている。
「お父さん、私、医者になるの。だから、お父さんの薦める音大附属には行かない。近くにある進学校にいく。――もう、決めた」
枕から顔を上げて、ベッドから起き上がって、見慣れた友人の顔を見上げた。視線を少し下にずらして、腕に触れる。震えている。
「自分の心の中をだれかにさらすのは、怖いんだ。叶うかわからない夢を語るのも、こわい。なれてもどうなるかわからない夢は、――もっと怖い」
須王は心を落ち着かせるように、深呼吸をした。
「陽はもっと怖かったと思うよ。誰からも期待されていない夢が開けて、夢のために、すぐに行動に移さなければいけなかった。自分に期待する家族を裏切ることは、期待に応えるのと同じくらい難しい。でもそこで、自分を曲げていたらきっと、家族への最大の、裏切りなんだ。自分が家族を好きである限り、家族に隠し事はしたくない。陽は懸命に悩んで、でもおじさんもおばさんも、光も好きだから、自分の気持ちに正直になろうとしたんだ。
それでも光は、まだ、陽を許せないか……?」
許せる、許せないじゃない。もうずっと前から、もう許せていた。気付かないフリをしていただけで、憎むコトで、自分の罪を、ごまかしていた。
「……須王、ピアノに、毎日さわることが出来てないんだ――最近にいたっては、学校以外で、弾いたことがない」
「…………」
「練習しても、上達しない自分が怖いんだ。練習しなくても上達しないなら、それはそれで仕方がないって言えるけど。努力が足りないって、最大限の努力って、どれを言うのか……わからないんだ」
「気付いてるよ、みんな。光の指は、ピアノをやっている人間のそれじゃない。それに去年の定期演奏会のあと、指にたくさんのマメをつくっただろう? 急にやりはじめたからだ」
光は自分の手を見た。何も出来ない手が、そこに在る。――屈辱的だった。
「光相手では、むこう二年分はしゃべったな。俺は教室もどるよ」
「須王!?」
「おばさんが口癖のように言うんだぜ? 男には、越えなきゃならない壁があるって」
須王が保健医に挨拶して、保健室を出て行くようすが、手にとるように見えた。再びベッドにもぐりこんで、光は一人で涙を流した。
知っていて、黙っている。気付いて、気付かないふりをする。もどかしさがきっとあった。でも、焦ることなく、そばにいて、日常を繰り返してくれた。長い長い、三年間もの間。睨む父は、きっと自分に訴えていた。
――お前は、その道でいいのか、と。
母はうつむきながら、主張しない自分の息子を恥じていたのだろうか。思えばまだ、誰にも言っていなかった。自分の正直な夢を。単なるプロのピアニストだけじゃない、自分の姿。描く将来像を、現実に押しつぶされて、言うのが怖くなってきた。叶う、叶わない。
叶うか叶わないかなんて、どうだっていいじゃないか。迷ったって、選べる道はひとつしかない。自分を追う風は、少しでも大きい方が良い。それで、いいじゃないか。
親愛なる、家族へ。まだ言っていなかった言葉が、あるよ。
夢の中で、描いていた。過去も、未来も。
サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>双子編第8話