サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
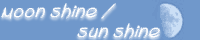
双子編第6話
夏は、嫌いだ。今でも思い出せる、素手から伝わった震えていた陽の肩。こちらを睨む父。こちらから視線をそらし、沈黙する母。偶然居合わせた友人。――それらすべてを思い出してしまうから。あの時父は、自分に何を訴えていたのか。陽のようになるな、だったろうか。陽をなぜ止められなかったのか、だろうか。
父は密かに、陽に期待していたのだから。俺よりも、陽。なんでもできる、器用な姉を、父は、期待していた。ピアノをすきなのは、ピアノを長くやっているのは、姉でもない、自分なのに。
姉を羨望しだすと止まらない。弱くなる、弱くなって弱くなって、どん底に落ちて……以前、どうやって抜け出せたかは覚えていない。でも、近付いていた高校入試を棒にふりかけるほど、荒れていたのは確かだ。
――私は、光くんの……
ふと、声が聞こえた。なつかしい声は、どこかで聞いた覚えがある。そう、たしか。陽の……。……陽のない自分の生活は、考えられないのか。
光は大きくため息をつき、制服に身を包んだ。
「あー、登校日が同じ日で助かるわ。陽の講習は時間がばらばらで疲れちゃう。サボってないでしょうね?」
お皿をテーブルに置きながら、母親の遊恵が話していく。なんらかわらない、朝の風景だった。陽が珍しく、目元にクマをつけている以外は。
「……学校で倒れないようにね?」
「う、平気……貧血にはなったことないし、単なる寝不足……」
「ダメだと思ったら、正直に保健室に行くのよ。――光っ! マヨネーズかけすぎっ!!」
光のサラダボールに異常な量を表したマヨネーズに遊恵が驚いていると、光は正気に戻ったのか、慌ててマヨネーズを止めた。尋常ではない量のため、小皿に余分を取っていく、地道な作業をしていくものの、残ったマヨネーズでさえ、普段の倍だ。
「ちゃんと食べなさいよ。マヨネーズかけすぎたのは、光なんだから」
隣でハムエッグを食べる陽が口を出す。渋々、フォークをとってサラダを食べ始めた光の顔は、普段よりも真ん中に収縮されている。
「光、そろそろでなくていいの?」
「そう、バスの時刻が変わったから、十分ぐらいは平気。陽は相変わらず……」
「まだ四十分の余裕はあるねっ」
ピースマークを前に出した陽が、光に笑む。陽の学校は自宅からバスで二十分、光の学校は、バス二十分のって駅に着いたあと、三十分ほど。始業時間も異なるため、光と陽では家を出る時刻に約一時間近くのずれが生じる。遊恵の希望で朝食の時間は統一されているものの、これから四十分、陽が何をしてすごすのか、光は知らない。
「じゃ、いってきます」
光が玄関から出て行くのを陽と遊恵が手を振って見送る。夏休み中でも変わらないことが、起きている。
「……ねぇ陽、光、また悩んでいるのかしら?」
「多分というか、絶対そう。お父さん、性格悪すぎだもん」
どうして結婚したの、と言外に匂わせる発言に、遊恵は苦笑するしかない。妻と夫で強いのは妻だといえるが、父と息子で強いのはどちらかといわれれば、黙るしかない。
「父親なんて、息子はいつか越えなきゃいけない存在だもの。私は手出ししないわ、甘くないからね」
「甘いって、なんかちがうよそれ……」
「じゃぁ、言葉をかえるわ。自分で自分を変えて、自分で乗り越えなきゃ意味がないことに、手出しはしない」
そういうと、朝食の後片付け専用の鼻歌を鳴らしながら、リビングに入っていく。単調なカノンではじまる一日を楽しんでいるのは、母だけなのかも知れない。
「私が手出しするのも、いけないかな……」
陽はつぶやき、自分のカバンを持った。乱暴に玄関をあけ、走る。
「いってきますっ!」
遠くで母親の声がしても、陽は走った。歩くのが早い光に追いつくまで、あと少し。
「光!」
それらしき後ろ姿を見つけると、さらに速度を上げて、陽は走った。人影が止まると笑みを浮かべ、止まった。振りかえる。
「あのね、あのね、光……」
「陽、――」
陽は一瞬耳を疑った。いつの間にか低くなっていた声は、言葉を確実に耳に届けていた。顔も、声も、何もみたくない、ききたくない。言葉はたしかに、そうつむがれていた。
「どうして、光。私、……だって、私はっ」
「追いつかないんだ、気持ちが。できる範囲で、だけど」
まるでそうするしかないような思いつめた表情のなかに浮かぶ、わずかな笑み。困ったように、だがその笑みは、すぐに隠されてしまった。
「俺はまだ、陽みたいに強くなれない」
「私だって、全然……一緒に、強くなろうよ……」
「だれかと一緒に強くなることはできない――陽が一番よく、知っているだろう?」
切り捨てた瞬間は、三年前。あの夏。
「ごめん、ごめん光。――だけど、――ごめんしか、言えないね……」
陽は顔を伏せた。光が、全速力ではしっていく。その速さは、陽の方が早く感じられる。陽はその場に立ち尽くしたままだった。芽生えた夢のために捨てたこと、かけがえのない家族さえも裏切って、決めたこと。でもその夢に、いくらの価値があるのか。家族にいくらの価値があるのか。――どっちが。
大切なものがどちらかなんて、決められるものじゃない。大切なものの価値に軽重はない。大切。大切。大切。――失いたくはないから、中途半端になってしまう。罪悪感ばかりが押し寄せてくる。
きっと気付いていなかった過去の自分が、羨ましいようで、にくい。
「ごめ、っ。ごっ、ごめ……」
「やっぱり陽ね。ほら、どうした? 路上で泣いてると、変なおじさんに連れて行かれるぞ?」
ここ数日の講習ではすれ違いの多かった友人の声が、上から振ってくる。しゃがんだ彼女に抱きつくと、一番最初に差し出されたのは二枚のハンカチ。
「制服は汚さないでね。自分の顔、ちゃんとふきなさい」
そのための、二枚。それさえ守れば、いいこと。陽は親友の胸の中で、三年分の涙を流した。
サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>双子編第6話