サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
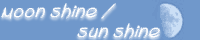
双子編第4話
父の曲をはじめて聞いたのがいつだったか、なんて覚えていない。父は時々留守がちで、時々飽きるほど家にいた。しかし家にいるときは大概、防音設備の整った部屋にこもって曲を作っていた……一曲に二束三文のような値しかつかなかったとき、父はそれでも作っていた。安ければ、大量に。まるで機械のようだと子供心に思いながら、母は自分達を、そんな父のつくった子守唄で、眠らせていたのだ。
父と違い、母は自分達に色々な曲を弾いて聞かせた。陽は大体すぐに眠ってしまっていたが、光はずっと、耳をすませて静かに聞いていた。それが今日、光の絶対音感を育み、陽の音感なしを作り上げたのかもしれない。
何歳かの、誕生日の日。父はありきたりなバースデーソングはイヤだ、と言い出して、即興で曲を作った。母がバースデープレゼントはそれにしたら、というと、父は微笑んでもう一曲つくった。自分達のため、だけに。
その曲はわずかな人間しか知らない、ヒミツの曲だ。いまでも誕生日にはその曲が演奏される。……今は、光と陽の連弾と、須王のヴァイオリンの旋律で。歌を歌える人間がいれば完璧だったかも知れないが、歌が上手い領域の人間は、周りにはいなかった。
父がつくったその曲を、自分で弾きたい……そう思って、光はピアノをはじめた。三歳。それからのめりこむように夢中になって、ピアノ以外のものに興味はさほどわかなかったし、ピアノのこと以外――父のこと以外――は、どうでもよかった。それでも、陽や母はかまってきたから、無視しきることは出来なかったけれど。
「ねぇ須王、どうして最近、光が冷たいんだと思う?」
夏休み中に限ったことではないが、陽が須王に「相談」を持ちかけるのは、最近では須王が学校の練習室でこもっている時、というのが相場になっていた。須王の練習室をどことなく当て、窓から顔をひょっこりと出して話し出すのだ。
陽にも陽のために使うべき時間があるはずだが、姉の責任感なのか、陽の思考時間の大半は弟で占められていると言っても過言ではない。残りの時間でやるのが勉強と読書とピアノで、それで第一志望の大学が安全圏といっていられるのだから、幸せな女である――と、須王は分析している。
「自分の胸に手を当てて、思い当たる節は?」
「……うーん、やっぱコンクール……?」
「オレもそれしか思い浮かばない」
「でもっ、……あ、そっか。――ああでも、……お父さんのバカぁ……」
顔と手だけがくるくると回り、表情と共に風が部屋に入ってくる。須王はため息をつくと、かばんにヴァイオリンをしまい、窓際に近付いた。
「ちょうど昼時だから、学食で食べるか? あそこなら、クーラーあるんだし」
「光がもう少しでも、須王みたいなたらしだったら楽だったのに」
「オイコラ」
本来なら見慣れないはずの他校に通う陽の顔だが、須王と光が通うこの学校では、ちょっとした有名人の顔だ。
他校カバン、制服を隠すことなく、音楽棟の練習室に向かい、須王と話している陽の姿を、練習熱心な生徒で見たことのないものはいない。噂が噂を呼び、須王のインタビューがあり、光の双子の姉であることが分かると、噂に拍車をかけた。
陽の容姿は、――光もそうだが―― 一般的に見て整った姿形をしている。美人という判断基準とは別の、「相手に悪印象は与えない」容姿というヤツだ。光は普段眉根を寄せているため、おびえる人間も少なくないが、陽は光曰く、愛想のカタマリだ。常に口許に浮かぶ微笑と美人ともブサイクとも言えない容姿は、「練習室のモナ・リザ」との異名を持つ……らしい。噂が流れているらしいことを知っていても、中身を知らぬは本人ばかり……でなく、その弱二名の身内さえも知らない。疎いタチなのだ。
「ああ、それで光が最近不機嫌だったのか」
湯豆腐を囲みながら父と話し、父が「陽の曲」を作りながら「光の曲」を後回しにした事実を、ミートソーススパゲッティをフォークに巻きつけながら、陽は話した。
須王の目の前の食事は、Aランチと呼ばれる、ピラフにスープ・サラダのセット、プラス三種の小鉢の中から一つで計四百円のものだ。ピラフの量がやや少ないのが欠点だが、小鉢をえらべば、気にすることはない、イイ値のランチメニューだ。
「夏休み終ったら、光たちのところ、すぐに附属進学に向けてのテストがあるんでしょ? 絶対光、落ちるよ」
「アイツはいつもメンタル面が弱いからなァ。高校のときも既にやばかったし。ギリギリだったんだよな、確か。おかげで親の七光り……」
「NGワード、一回」
須王はおとなしく財布から百円を出した。
「……NGワード制も、はや三年か……」
「ホント懲りないよね、須王。これであたしにいくら貢いでるか知ってる?」
須王は無言でスープに手を伸ばした。舌を焼けどして、罰の悪そうにする彼は、陽にとっては光の次に面白い弟のようなものだ。光と違うところは、時々兄、と言いたくなるほど大人っぽいところが油断ならないあたりか。
「どうして双子なのに、お互いの気持ちがわかんないんだろうねぇ……」
「どうして双子なのに、そんなにブラコンになれるんだか」
「えーっ、あの可愛さがわかんないの!? 人生の楽しさを知らない奴だねェ!」
「……悪趣味だ、お前は」
須王と陽の付き合いは、実は光と須王とのそれよりも、長い。三歳の頃からピアノを習い始めた光は、大体において今と変わらず、周りが恐怖を覚えるほどにピアノに没頭した。一方陽は、そんな光の相手をしながら――別名邪魔しながら――、ピアノは一切せず、母の職場に遊びに行っては、気ままに音楽を聞いたり、教室に通う子供と外で遊んでいたのだ。無理強いしなかった両親に感謝すべき、と思うのは、この時間が楽しかったからだ。
須王との出会いも、教室で遊んでいたときなのだ。光と須王が出会うのは、それから数年たって、定期演奏会で演目の順番が近くなった頃だった。
「悪趣味で結構。大体そんなの知ってるでしょ?」
最後の一口を放り込むと、陽はじっと須王の顔を見つめた。ピラフがまだ三分の一ほど残っている須王は、よくかんで食べるため、食事がスローペースだ。人としゃべっていると、Aランチ四十分もざらではない。
「はじめてあったときは、そらもう、かわいいオンナノコだったのになぁ……」
どこか遠い目で陽を見つめる須王に、陽は眉間にしわを寄せつつ、お茶に手を伸ばした。自分のお茶がいつの間にか増えていることに気付き、目の前の男の周到さに驚くのだ。
自分が男だったら絶対嫁にもらってたわ。
そう心密やかに思うも、ちょうどよく性別が違った現実を考えて、恋愛感情が沸くかというと別だ。将来のことを考えると、成功する人間が極わずかしかいない世界に住む人間はアウトと思うし、何しろこいつには初恋を壊された過去がある。
「あーあ、はじめてあったときは、どこぞのお嬢様かと思ったのに」
未だに中性的な顔立ちが残る須王にとって、そこが滅多にない弱点だったりするのだ。結局、お互いに昔話の論争となり、肝心の議題――愛しき光についての話に、進展はなかった。
サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>双子編第4話