サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>
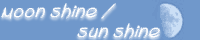
双子編第2話
「シズク音楽教室」といえば、大手楽器チェーン「シズク楽器」直営の音楽教室として、名高いといえば名高い。ただ教室は全国規模になく、点々と散在し、存在感としてはかけるものがある。
その存在感を一気に際立たせるのが、半年に一回、各教室ごとに行われる定期発表会だった。連弾やヴァイオリンとの合奏、技術・芸術性共に、プログラムの後半、年齢が高くなるにつれて上がってくる。全国コンクールもかくや、と思わせるその質は、「シズク音楽教室」の小規模ながらも質の高いレッスンの証拠だ。
西尾陽と西尾光の母は、そこでピアノの講師を勤める「働く女」で、彼らの父親はソロのヴァイオリニストとして活躍中の男だ。音楽との縁は祖父母の代から続く、音楽一家である。
「光、ちゃんと待ってるんだよ? 帰ったら、思いっきりいじめちゃうんだから!」
言い残して、陽は防音設備の整ったレッスン室に入っていく。ドアが重たげに開くと、わずかな会話だけを残して閉じていく。陽の講師は母親だ。
「陽もお前にべったりだな」
先ほどひと悶着のあった須王が、黒いケースを片手に、光の座っているベンチの隣に座った。差し出された缶コーヒーを受け取ると、これでチャラだな、と小さくつぶやかれた。いじめはいけない、という自覚だけあるらしい。
「べったりじゃないよ、ただのコミニュケーション」
「かーっ、イカン、イカンよチミ!! 彼女もしくは彼氏いない歴十八年を、双子で守ってどーする!?」
「俺はピアノが彼女だから」
一人でもだえる須王を尻目に、光は缶コーヒーを飲み干し、空き缶入れに向けて放り投げた。四十センチ四方のダンボール箱に「空き缶」と書いてあるだけの簡素なものだが、分別ごとにゴミ箱を用意する余裕があったらピアノ一台、という方針のもと、ビルの中は質素にできている。
光は立ち上がると、須王に向かっていった。
「俺、先に家帰って夕飯の支度してるから。須王、陽待ってて」
「義理がないはずだが?」
缶コーヒーでさっきのイジメはチャラだ、といわんばかりに自らの分の缶を見せる須王に、光は笑っていった。
「バーカ、今日の昼のパンをおごってやっただろ」
「……そんなの」
パンと言っても購買で売っているドーナッツ一個六十円だったはずだ。それこそ缶コーヒー 一本百十円に比べればたいした額じゃない。それでも光はばたばたと階段のほうへかけてビルを出た。
陽のレッスンは普段よりも早く、レッスン室にはいってからものの三十分と経っていなかった。
「なんか次の子がはやめに来るからってことで……」
レッスン室の扉を開けながら出てきた陽が、ベンチに座っている須王の顔に目を丸くする。その隣にいない、光のかげにも。
「……須王。光、帰っちゃった?」
「ざっつらいと」
「ふーん……」
目の前の自動販売機に小銭を入れると、缶紅茶を一本持って、須王の隣に座った。
「オレの分はないわけ?」
「自分の手の中、見て言えば?」
須王の手中には、光に買ったものと同じ缶コーヒーがあった。プルは開けず、ずっと手で握り締めていたらしかった。陽がまったりとベンチで紅茶を飲んでいる間、須王は冷たいコーヒーを飲まずに、じっとどこかをみつめていた。
「ね、聞いた? 今度の定期発表会のお話」
「つい一時間ほど前に、おばさんから」
「――お母さんから、か。私も、さっきのレッスンで聞いた……ってか、それだけのレッスンってのはひどいよね」
二人の間には音がない。
「……光に、なんて言おう……さっき、連弾楽しみだねっていったばっか……なのに」
「アイツ、不用意な発言で困惑させるなよ。そろそろ音大の推薦が、かかってるんだから――」
「だよね!? あーっ、どうしよう、高校みたいな事があったら……」
空き缶を持ちながら頭を抱え出した陽に、須王は驚き、思わず手と缶コーヒーを出した。
「ありがと、須王。コーヒー苦手なの、知ってるのにね?」
最後、陽は笑みを浮かべた。小さな頃から変わらない、何かに耐えているような、そんな笑みだった。
サイトトップ>『moon shine/sun shine』目次>双子編第2話