サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
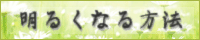
第2部 第10話
病院に行って、まずするのが採血。
看護婦さんに手放しで褒められるほど、私の腕は「針がさしやすい」そうだ。まあ、小さい頃は入院で点滴もしょっちゅうだったから、それくらいの身体的優位がなければ、とっくに病院拒否だろう。このにおい、雰囲気だけで滅入ってアウト。実はこの定期検診も、避けて通りたい。
母が典型の「針をどこにさしたらいいのかわからない」タイプで、娘ながら、遺伝しなくてよかったと思う。
採血結果が出ただろう頃に呼ばれる。運がよければ30分。長いと、一時間近く。今日は珍しくお年寄り少なめで、窓口の混雑も目立たない。
呼ばれて行くと、いつもの先生。
「久しぶり〜。アナタのママから携帯に電話きて、びっくりしたけど、なにもないわよぅ。」
母、直接医者からアポを取ったのか……
私が手のかかる患者だったせいか、母と医者がつーかーのような仲になったのはすぐだった。年が近いせいもあるだろう。ただ、ヒモの彼氏はいても独身貫いてる先生が、とくに他の大学病院に動かずこの病院にいるのは奇跡的な話だ。
言い方によっては、私の身体を私以上に熟知している。
「なにかあったら、とっくにベッドに縛り付けられてますよ」
「まーね〜。でも、ちゃんと来たのは偉い。イブなのに、予定ぐらい入ってないのー?」
「……予定は、ありますけど」
「どうせ塾とかいうんでしょ?」
「……」
なんかこう。……悔しいけど、去年はそうだっただけに、言い返すのもなぁ。
「ちゃんと、……予定ですよ」
「あらあら。ボーイフレンドでもできたの?」
「彼氏というか。……よくわかんない」
「なになに、恋バナ?」
このすり寄り方、とても41には思えない。
「好きとか、よくわかんない。惚れてるとか、愛してるとか、それって、目に見えないでしょう?」
「目に見えたら、苦労しないわねぇ。なに、振り向いてもらえないの?」
首を振る。振り向いていないのはむしろ、こっちの方だ。ずるい。ひどい。
「まあ、年齢の割に数少ない経験でアドバイスするなら、お互いに好きでなければ、たぶん、すぐに終わりは見えるわ。互いにほれあってれば、お互いに努力するけど、片方だけなら、すぐ疲れて終わり」
「片方、すごく諦めが悪かったら?」
「どんなタフな人でも、一方通行の感情って、結構辛いものよ? どっかで、
折れることが大半。ずーっと嫌っていたはずなのに、相手が嫌っていなかったら、いつのまにか忘れる。それと一緒。一方通行でも好きだった、彼氏彼女になった。そうしたら、お互いに好きあうようになるか、片方疲れて諦めて終わるか、どちらか」
「ほんとに?」
「大人の助言、素直に受け取っておきなさい〜。片思いが長引くのは、好きだっていう感情と、他人のしらない秘密の感情を抱えた分、特別に思えるから。伝えた片思いは、もう片思いじゃないのよね。初恋は尚更」
「最後に、一つ」
診察は終わってるんだろう。
「ひみつじゃない片思いって? どうなるの?」
「気持ちを伝えたら、こたえて欲しい、欲求になるのよ。人によっては相手を思いやる余裕もあるけど、逆に、余裕がなくて、自滅するタイプもいるわね」
間違いなく、私をそのタイプと分析しての話だろ。
待ち合わせた図書館で、机で勉強をしていたら、かなり意外な人にであった。
「一樹、勉強か?」
「……父さん」
笹本くんの、父。
「偶然だな」
「嘘だ、絶対狙って来ただろ!!!!」
思わず声を荒立てた様子の笹本くんに、静粛と同じくらい静かな目線がいくつも突き刺さる。
私は、お父さんの視線を痛いくらいに……感じます。
「間違えていたら申し訳ないが、君は青木さんかな?」
「は、はじめまして、青木……李花です」
「はじめまして、一樹の父で、笹本哲郎です。一樹がいつもお世話になっています」
「よく知ってるね?」
笹本くんが言う。紹介もしていないのに。PTAとかで知ってた?
「お母さんとお仕事上の付き合いがあるんだ。よく勉強会でも拝見するしね」
「そういえば、先日伺ってます……」
先日と言うより大分前になるが、三者面談の時に話を聞いたよ、そういえば。
「私の調べ物は終わっているから、私はこれで」
「はい……」
「いつでも我が家にいらっしゃい、青木さん。学校での一樹の話も聞きたい」
私が知るのは、完璧超人に近しい、あなたの息子の姿ですけれども。
そんなことを思いながら、去りゆく後ろ姿を見つめる。笹本くんは、未だに悪態だ。
「最悪だ……」
よく見ると、耳元が赤い。そうとう、恥ずかしかったのかな。うん、私も三者面談の時は恥ずかしかった。
「あ、私は、気にしてないよ?」
「気にしたら凹むから……」
「元気だして!」
安い応酬かなと思いながら、そんな言葉しか出ない。自分が母にこの現場をみられたら、ひたすらひたすら気まずさで固まるじしんがあるだけに、やりとりしていた笹本くんは若干、尊敬したんだけど。
「青木さんが、わがままきいてくれたら、元気出す」
なに!
「名前で呼んでいい? なんか父親と同じって、凹む」
「いいよ」
「ほんとに?」
「うーん、ためらうことでもなくない?」
「……そっか。……りか、……ちゃん?」
あー、そうきたかぁー。
「ごめん、ちゃん付けはダメ。呼び捨てちゃっていいから」
「だめ? りかちゃん。」
明らかに理由は分かり切ってる風の、からかい口調を、最近ようやく見分けのつくようになった。
「ダメ。同名の人形、好きになれないしそんなかわいくないし」
「そんなにかわいい理由?」
「かわいくないし」
「――りか」
言われて、気付く。
「え、なに、どうかした? むしろ、なにかした?」
「ちが、……違うの」
響きが違うのだ。まり先輩とも、母とも、冴島とも。――あまくて、響く。
「なんでもないよ」
それほど大切にされているのかと思った。
それに見合うものをかえせなくて、申し訳なくて。
名前を呼ばれて一瞬よぎったのは、……冴島だったけれども。
「勉強、しようか。」
ことばにしなければ。
月日とは残酷かつあっという間に過ぎ去るもので、受験シーズンを飲み込み、卒業式の日だ。
真理先輩は方々の予想を覆し、難関の第一志望に合格した。いわずもがな、高崎先輩の高校だ。仲のいいことで。
在校生として、式に出席しながらも、なかなか実感がわかない。明日には真理先輩が学校にはいないことを、知っているはずなのに。
それを、確信として持てなかった。
式が一通り終わり、昼休みを迎えると、真理先輩からメールが届いた。屋上集合。なんだろうかと疑問に思いながら、了解と返信を打つ。……笹本くんにも言われたけれど、相変わらず素っ気ないメールだよな。こういうの、やっぱり改善の余地があるんだろうか。
訥々とした思考をめぐらしながら、お昼休みになる。卒業式後の在校生の仕事はさほどなく、明日の終業式に備えての大掃除だったり、体育館の椅子を引き上げたりといった雑用に終始する。
「冴島、屋上行くでしょ」
「……ああ」
同じようにメールが来ていた冴島を誘って、屋上に向かう。笹本くんがすこし教室で目があったけれども、なにもせずに教室を後にする。真理先輩の、用件もわからないしさ。それになんとなく、冴島の隣をのろのろと歩くことに、すこしだけ笹本くんに申し訳ない気持ちを感じる。べつになにか、……あるわけじゃないけど。
「真理先輩の用事、なんだろうね?」
「さあ」
嘘だ。気にならないはずはないと思う。けれどもそれは指摘せずに――なぜなら、それが私と冴島の距離感だから――屋上へ向かう足を、一歩、また一歩と増やしていく。
「私、同じ屋上にいても、あまり冴島と話した感じがしないなぁ」
「名に、いまさら。」
「や、結局二年間同じクラスだし、接触回数として考えたとき、冴島ってそこまで仲良くないのかなって」
「……俺、お前のこと嫌いだったしな」
だった! 過去形で救いがあるとはいえ、なんてことをさらっというんだ!
「第一お前のほうこそ、真理にべったりだっただろ。あんな女同士の会話、入れるか」
あー、これは、冴島なりにきをつかってくれたってこと?
「気にしなくて、よかったのに。同じ場所にいるんだしさ」
たしかにたしかに、冴島からしたら、わたしは真理先輩を途中から独占した侵入者かもしれない。わたしにとって、高崎先輩がそう思った。
「真理先輩がいなくなったらさみしいね」
そんなの、当たり前だ。でも、別れる実感言葉で作ろうとした。
「別に」
「嘘ばっか」
真理先輩がいて、屋上があって、それがひとつの完成された世界だった。
「真理先輩がいなくなったら私たち、どんな関係になるんだろうね? 友
達?」
「それはないだろ」
「普通、即答する? そこ」
「だってそうだろ」
指摘。たしかにね。
「でも、それでいいんじゃないか。なんの関係も横たわっていない、ただの関係でも。互いが空気みたいに、なにもない感じで」
うーん?
「だから話せることとか、あるだろ。お前、あんなにないてばっかだったんだから。それじゃだめか?」
言われると、なんだかなにもいえない。
残酷な男だなぁ。
階段を昇っていると、明らかに毛並みの違う人に出会った。高崎先輩。真理先輩の、彼氏だ。文化祭以降、反省会で一度あったきりの高崎先輩は、久しぶりに見るとなんだかやつれたように見えた。高校2ねん、3月。大学受験でやっぱり忙しい時期なのかと、私にはそれぐらいの想像しか及ばない。
「真理によばれたんでしょ?」
「先輩もですか?」
「いんや、俺は立ち会い」
なんだろう、不意に、怖くなった。
……屋上に行くことに、はじめて足をすくませた。
「なんの、立ち会いですか?」
足がすくんで進まない言い訳の代わりに、立ち止まった足の代わりに、高崎先輩に向かって尋ねる。
高崎先輩は、こけたほおをゆるめて、ほほえんだ。そうして、なにも知らないんだという代わりに、首を横に振った。私は、そう思うしかなかった。
冴島は高崎先輩を見て、明らかにぴりぴりし始めた。教室に帰りたい――そんな感情がよぎった。でも、真理先輩が。真理先輩が読んでいると思うと、それは無碍にできなくて、自分を奮い立たせるように手をぎゅっと握って、力を込めて、足を踏み出す。
屋上の扉を開けると、胸元に花を挿した真理先輩がたたずんでいた。
――ああ。この人は、もう、いなくなるんだな……
きっと卒業したら、この人にはもう会えない。その確信が、なんだかあった。同じ高校に行く。私が合格すればそんな未来もあるはずなのに、キッとその未来にいる真理先輩と、いまの真理先輩には隔たりがあった。
違うのだ、変わってしまうのだ。あの夏のように。
「ああ、来たのか」
ふと、違和感と懐かしさを感じた。なぜだろうかと思って、あの、出会ったときの口調に似ているのだとすぐ気づく。ここ数ヶ月の、妙に丁寧な……女の子らしい真理先輩の話し方とは、一線を画して。
「冴島も李花も、突然読んで悪いな。用があったんだ。返してもらおうと思って」
「なにを?」
間髪入れずにたずね、すぐにそれが愚問だと気づいた。屋上で借りた、唯一のもの。
「――鍵を」
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第2部 第10話