サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
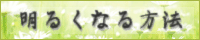
第2部 最終話
「本当は、……あのときは、あげたつもりでいたんだけど。もう、二人にはいらないと思って」
ずっと、ずっと、持ち続けていた鍵。別にそれは、意識していたわけではないけれど、いつも制服のポケットに忍ばせてあった。使った回数は片手で数えられる。だっていつも、真理先輩か冴島がいたからだ……否、二人がいるときにしか、私はそもそも、屋上を使っていなかったように思う。
でも、確かに最近は、教室にいる時間が増えた。逃げるように図書館や屋上にいた時間、文化祭や笹本くんとのことがあって、確実に、1日に屋上にいる時間は減っていった。
私は、真理先輩のいなくなった屋上に……きっと、来ることはできない。
そう思うと、鍵を返すのは必然のように感じられた。目の前の真理先輩が、以前の真理先輩を装っている風で、けれども中身は全然違う、私の知っている真理先輩との齟齬を感じたせいもあるかも知れない。
泣きたくなるほど、真理先輩は変わった。――いい方向に。今と昔を比べて、昔がいいという人はいないんだと思いながら、けれども、私は、昔の真理先輩が好きだった。
変わらない、変わっていないと思うけれども、そう思いたいだけで、実は、気持ちはとっくに離れていたのかも知れない。
「真理、……先輩」
ポケットの鍵を取り出すと、先輩は笑みを浮かべた。優しく。美しく。
今までにない柔らかなほほえみを浮かべた真理先輩は、けれども、私の知っている真理先輩とは余りにも遠くなっていた。高校でまた会いましょうなんていえなかった。だって、……未来、会える真理先輩は、変わってしまうから。
「いままで、ありがとうございました。卒業、おめでとうございます」
「ありがとう」
キーホルダーもなにもつけていなかった、素っ気ない鍵を渡す。いてもたってもいられなくて、その場を後にした。ああだから、高崎先輩は立ち会ったのか。屋上のドアの前にいたその人の顔を見て、気づく。
振り返ると、微動だにしない冴島の姿があった。きっと、私以上に去来する思いがあるんだろう。なんだか他人事には思えなくて、ふと、屋上の扉の脇に立って、傍観することに決めた。高崎先輩の顔を見たら、先ほどまでのここにいてはいけないような、そんな気持ちが薄らいだのだ。
部外者のいる、屋上。それが二度目だと思い出しながら。
「冴島、なんて声をかけたらいいのか、わからないけど。……ありがとう。冴島がいたから、私は学校に来れたし、そのぶん、大分出席日数は助かった」
「俺は、出席日数の助けになっただけかよ」
「他にもあるよ。……ただ、なんだか、浮かばないんだ。いろいろあって、いろいろかわって、いろいろなくなって」
「じゃぁ、あいつはなんだよ」
あいつ、というのが高崎先輩を指すだろうと、すぐにわかった。
「真理にとって、あいつはなんだよ。俺は何だったんだ? ……あっさり見捨てられるのか」
真理先輩の表情がよく見えた。冴島の表情が、なにもわからない代わりに。
「そんなつもりじゃ……」
「見捨てるんだよ、真理」
立会人が、口をはさんだ。
「いつまでも甘えて、よりかかるしか脳のない、弟もどきは見捨てるんだ。断ち切るんだ。そうしないと君が、いつまでも失った弟から解放されない。君が、かわれない」
「好きなんだ、真理」
「冴島?」
「好きなんだ、真理。初めてあったときからずっと。……ずっと。弟の身代わりだって知ってる、それ以上の感情がないのも知ってる、でも、……なんであいつとつきあうんだ? なんで、あいつなんだ?」
「冴島」
顔がわからない。言葉だけが聞こえる。それだけで、私は打ちのめされていった。冴島の告白なんて、聞きたくなかった。真理先輩への告白なんて、聞きたくなかった。
「ごめん、冴島」
ただ一言で、真理先輩は冴島に応えた。けれども何度も繰り返して、嗚咽が混じり始めたその声を、チャイムがかき消すまで、ずっと。
立会人が真理先輩の退場を促し、冴島が罵倒するまで、ずっと――ずっと、謝罪をし続けていた。
「君たちも、これから終礼だろう? 戻らなくていいのかい?」
憎き恋敵に言われた冴島は、そのままそっぽを向いて屋上から去った。とうてい教室に戻るとは思えなかったけれども、どこに行くのかなんて私にはわからない。
「高崎先輩、一つ聞いていいですか」
「応えるかわからないよ?」
それでいいですと応えて、訪ねた。
「真理先輩のこと、好きなんですか? 好きで、つきあっているんですか?」
「君が、それを聞くの?」
「私のことなんて、放っておいてください」
「なら、僕たちのこともそうだよね? それとも、応えなきゃいけない義務や貸しがあった?」
このひと、絶対性格がゆがんでる……そう思いながら、答えを待った。気まぐれな人。
「好きだよ。真理のことは愛している。今まで好きになったどんな女の子よりも、真理が一番、いとおしいよね」
ただ、と逆説を続けた。
「真理は、自分が愛されている自覚なんてないよ。そういう子だから。でもって、俺もそうだから。……俺たちはお互いに、一生、『互いに惚れあってる』片思い同士だね」
「……なんで、つきあっているんですか」
「それは秘密。というか、言っても君にはわからないよ。笹本になら、わかるだろうけどね」
顔が赤くなる。この人は、私と笹本くんがつきあっているのを確実に知っている!
「君の感情は、まだまだどこか純真だ。リベラルだ。だから、無意識に傷つけていることを知らないんだろう。だから、笹本は苦しい。けれどもそこが好きだから、なにも言えない。本当はすごくすごく、」
「高崎先輩!!」
制止する声。――笹本くんだった。
笹本くんが登場するやいなや、高崎先輩はいなくなった。
笹本くんになんて言えばいいのかわからず、私はただ、立ち尽くしていた。
「……李花」
クリスマスイブ以来、はじめて、改めて呼ばれた自分の名前に、緊張が走った。
「なに?」
思えば自分は、そのときおそらく自然にあるだろう……笹本くんという呼び方を変えることには至らなかった。今更気づいたのは遅くて、李花、と呼ばれたのに習えばいいのだろうことに憶測はついても、けれどもためらいが強くて、そうは呼べなかった。
「俺が思っていること、知りたい?」
なにも言えない。黙っていると、笹本くんが、私の手を取り、握った。
「李花に、……触れたい」
クリスマス以来、久しぶりに聞いた声は、少ししか離れていなかったにもかかわらず、声変わりをしていた。
「生徒会選挙の時から、ずっと李花を見ていた。きっかけは悔しいことに冴島なんだけれども、四月に一緒のクラスになったときからずっと気になっていた。でも、ずっと、李花は……俺を視界に入れてはくれなかった」
文化祭の時の告白と、すべてが違っていた。質感が。熱量が。
「視界に入りたかった。彼氏になって、視界に入れたつもりだった。でも、視界には入れても、思考には入れない。気持ちがない。目線がこちらに向いていて、けれども空虚なんだ。満たされないんだ。俺は李花が好きなのに、李花は俺が好きじゃない」
「そんなことっ」
「……嫌いじゃない、のは、好きだというのと一緒じゃない。むしろ、無関心に近いんでしょ?」
聞きながら傷ついて、でも、言っているこの人のことを思ったら、そんなことは口にできなかった。
「李花に触れたくても、好きだから触れたいのに、嫌いじゃないから近づけない。……高崎先輩が、俺にはわかる、意味がどんな言葉か想像できる?」
握る力が、いっそう強くなる。
「君はすごく純真だ。君はすごくリベラルだ。そんなところが好きなんだ。そういうところを知って、好きになったんだ。だから、なにもいえないんだ。
も本当は、本当は、」
本令のチャイムが鳴った。優等生の笹本くんが屋上にいるなんて、誰も想像できないだろう。終礼が始まるのに、笹本くんがいないなんて、きっと教室ではパニックだろう……笹本くんのことだから、そんなことも想定して、クラスメイトに一言言っているかも知れない。
そんな、わけもないことを考える私を現実に戻すように、笹本くんの顔が近づいた。目線があうのが怖くて、目をつむる。――生々しい感触が、唇をよぎった。目を開けたとき、視界に笹本くんの顔はない。耳元に、熱を感じる。
「李花、君を束縛したい」
そう言って、耳元から顔を遠ざけた。
いるような目線。手を握る、強い力。――気づけば、ずっとずっと、低い声。それは、男の人のもの。
そばにいることに、ずっとずっと、気づかなかった。
ササモトカズキくんは、男の人だった。
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第2部 最終話