サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
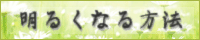
第2部 第7話
お母さんが出張から戻ると、学校はテスト期間に入った。全期間三日しかない中間だけれども、久しぶりに文化祭から隔絶された一日に、けれども二日目になるとすでに物足りなさを感じていた。
そんな、火曜日。
「李花、定期検診行ってないんだって?」
昨日、病院から電話があったんだけど――という前振りで、嫌な予感はしていた。
病院から電話があったというのははったりで、おそらくお母さんからかけたのだろう。平日は仕事の都合で病院に電話をかける時間がないから、平日休みをコレ幸いとかけたに違いない。
そんな推理をしても無意味なことはわかって……いるけど。
「やーだって、最後に発作起こしてから五年近く経つし……もう平気かなーって……」
中学生にもなって、大学病院の小児科通いというのは行きづらいというささやかな葛藤もあるが、それは隅に置いておく。この手のことについて、母に逆らうとろくなことがないのは経験則で知っている。
「自分の体のことなんだから、後で困るのは、李花自身よ? 幸いテスト週間で午前中だけなんだから、明日には行ってきなさい」
「でも明日は、委員会あるし……」
「委員会って言っても、五時間六時間やる訳じゃないでしょ? 病院は十六時に予約を入れておくから、絶対、行くのよ!」
たぶん、コレも行かなかったらお母さんの携帯に連絡入るんだろうなぁと言うことは、想像に難くない。
「わかった、いきます」
委員会は二時間ぐらいだろう。よほど議論の白熱しない限り。
結局時間内に終わらず、あとの話を支倉さんに任せて私は病院に行った。
「うん、問題なし」
身体測定された後、血液からレントゲンから、一通りの検査をした。結果が出る頃には、冬に近づいた外の景色は闇に覆われていた。
そんななか、検査結果をざっと診た担当医の先生があっさり言う。
「まぁもともと、子供は体が大きくなっていけば、健康になるものなんだけれど。李花ちゃんの場合、ある意味最初で躓いていたから、その影響が後々でないよう、見張るための定期検診なのよ」
暗に、間が開いたことを刺され、顔をしかめる。
幼稚園の頃から私の身体を知り尽くしている担当医の名前は、佐藤先生という。私が小さい頃も、今も独身の、とても年齢なんて読めないような四十歳。
ちなみにお母さんと同い年。
「それに、ちょっとしたきっかけですごく悪化することもあるからねぇ。去年と一昨年は、インフルエンザの予防接種受けたんだっけ?」
「受けてないです」
受けろと言われた記憶もなくはないが、学校全体での流行もなかったため、さほどうるさくいわれなかった。
「んー、できれば受けてほしいんだよねぇ。小学校卒業した以上、さほど敏感になる必要はないんだけど、そもそもインフルエンザ事態が悪化すると怖い感染症だし、合併症で死亡、なんて事例も毎年必ず報告が挙がるし」
うけるとしたら、今の時期っていい時期なのよと、まるで営業のような話しぶりだ。悪い人ではないし、本当に心配してもらっての言葉であることは重々承知しているけれども、何だかなあと思ってしまう。
「中学に入ってからは風邪知らずだし、大丈夫ですよ」
「過信はよくないのよ?」
「気をつけますから!」
「まぁ、大丈夫だとは思うけど、できれば次、四月ぐらいにはきてほしいなぁ」
正直、その頃には、忘れてしまうんだよね……
声に出したら怒られそうなことは心にしまっておく大前提で、先生の話を上の空でうなずき返す。たぶんコレは先生も「聞いていない」ことを織り込み済みで話しているのだろうから、慣れたやりとりだ。
いつものように「薬を出すほどでもないけど、身体には十分気をつけること!」というおきまりの文句を背中に、診察室をである。
会計を済ませて病院をであると、バス通りまでの電飾がやたら寒々しさを醸す。もう、十一月だからなぁと、ほどよくなったセーラー服の長袖に、心持ち、身を縮ませる。
冬が近いと感じさせる。きっと、文化祭が終わって一段落する頃には、紅葉も始まっているんだろう。
そうしてまた、巡っていく感覚がある。
「……あ、コスモス」
すでに咲きそろった花壇を見て、秋の気配を胸一杯につめこんだ。
「で、どうだったの? 病院」
委員会が終わると、支倉さんからそんな質問が飛んできた。「べ、べつに、心配してる訳じゃないよ?!」
あー、ツンデレってコレかーと思うような、そんな反応。気になってたんだよねぇ、やっぱり。私があんな風に途中で退席するのは初めてだったし。といっても、逐一説明するのはやや面倒なんだよなぁ、心配されてももぞもぞするし。
「んー、風邪気味だっただけなんだけど、親が心配して無理矢理病院の予約入れただけだから」
「へぇ、青木さんの家って、過保護だねぇ」
「小さい頃によく病気したから、そのせいでね。今はほとんど平気なんだけど。支倉さんは? 風邪とか平気?」
「全然心配ないよ〜親も兄弟も、みーんながんじょうだけが取り柄だもん」
そういって、支倉さんの家族の話に移っていく。ちょっと相づちを打ちながら、委員会で配られた文化祭前日から当日中のスケジュールを確認する。
……まったく、中学生の文化祭のくせに、なんて重いスケジュールなんだ。文化祭は土日の二日間開催で、準備期間として木曜日と金曜は授業がなくなる。私たちの係の出番は主に、この準備期間。当日の出し物は部活動単位になるから、私は暇、支倉さんは日曜日のサッカー部の練習試合以外は手が空く。
物品を管理する都合上、他の係と共同で倉庫代わりにしている教室の立ち番がある。これはすでに当番が振られていて、スケジュールにそれも書き込まれている。
まぁこれは、問題ないか。
当日の物品で間違いがないようにするためのリストは支倉さんに作ってもらったし、大丈夫だろう。
「――は来るの?」
「……え?」
集中していて聞こえなかった。聞き返すと、支倉さんはあくびれもせずに言い直した。
「だから、青木さんは、家族くるの?」
「ああ、うん、……来る、のかなぁ?」
母親に文化祭の委員になったことは言ったけれども、そういえば文化祭に来るとか来ないとかって言う話はしていないよなぁと思い出す。運動会ですら、きたり来なかったりがその時々で決まるのだから、一概に来るとは断言できない。
それに文化祭と言っても、出店が部活単位である以上、帰宅部の私はお呼びではないのだ。駆け込みみたいに途中入部する子も中に入るが、たいていは帰宅部のまま気楽に過ごすらしい。笹本くんに聞くと、帰宅部員の比率が多いと委員会の議題に取り上げるようだけれども、二割に満たない現状では余り問題にならないらしい。
「青木さんって、家族にも結構ドライ?」
母子家庭って言うのは知らないみたいだ。別に隠すほどのことでもないし、人によっては保護者欄に母親の名前が書いてある時点で察する人もいる。
「うーん、そうかも」
家族に対するスタンスは、きっとホットよりもクールだろう。
「それって、彼氏とかに対しても?」
それは。
そもそも、彼氏がいないのになんて応えるべきか。いやでも、笹本くんに告白されたときも、対外的に観たらすーっごく動揺しているようには見えなかっただろうし、自分でも冷静な対処を心がけていたんだから。
端から見たら。
「うーん、ドライかな……」
苦し紛れに応えると、そっかぁと納得した風で、会話が途切れてしまった。タイミングがよかったので、さっきつらつらと頭の中で考えていた準備期間中の段取りを確認すると、特になにも言われるでもなく了解が取れる。
ふっと笹本くんをみると、あちらもあちらで忙しそうだ。たしかに、緊張感は生徒会の方が、委員会の何倍もあるんだろうなぁと心中を察する。ほんとう、ご迷惑をおかけしましたと心の中で謝る。
支倉さんと仲良く相談していると、片瀬くんが訳知り顔で小突いてきたので、こちらも小突き返す。うーん、なんとかなってよかった!
日に日にそうして、文化祭が近づいてきた。
構内のざわめきも、日を追うごとに、大きくなっていく。
とうとう、文化祭の準備期間が始まった。
水曜日の放課後からこっち、ずーっと係の仕事にかかりきりだ。備品の数を確認してまとめて、支倉さんにダブルチェックを依頼。一度に数が全部そろえばいいものを、搬入の関係という大仰な理由で直前に来るものもあって、何度も同じ手順を踏む。
全部来てからやろうとすると、今度は二人では追いつかないのだ。
支倉さんも練習試合近くの忙しい中で、ちょくちょく顔を出してもらいながら、個数の確認というかなり地味な作業をしてもらっている。私は、初めて塾を休んだよ。もちろん事前に言って、振り替えの授業日程もとっているけど……自分の中では前代未聞。
その甲斐あってか、当日に個数の不足によるブーイングはなく、すんなりと終了した。例年受け取りの遅い団体というのがあって、それは相変わらずだったけれども、たいした数ではないので、支倉さんに留守番を頼んで各教室を回る。
ところどころ、不足しているから増やせないかなんて話をされるが、かなり冷たくあしらって終えた。初日さえ乗り切ってしまえば、あとは楽という前評判通り、準備一日目を怒濤の勢いで終えると、二日目になると仕事がなくなった。
全くない訳じゃないんだけどね。
大型の備品を取り扱う係の片瀬くんが座っていたいすに座り、バトンタッチ。
……備品倉庫の立ち番という、この上なく地味な仕事だ。四人で一日二時間ずつ、交替で見張る。初日でお互いにはくものははいてしまったので無断で持ち出す生徒対策だ。
「支倉さんじゃなかったっけ?」
「練習試合の準備でいろいろ忙しいみたいだから、引き受けたの。どうせ私、部活ないし」
「もぐりこまなかったんだ?」
帰宅部の生徒が一時的に他の部活に潜り込む例も多い。でなければこの期間、本当になにもすることがないのだ。居場所も図書室しかないのに、出席日数はきちんとカウントされるものだから、嫌煙する生徒はひたすらいやがる。
たぶん自分も、委員になっていなかったらその部類だが。
「委員会の方もあったしね。片瀬くんは? 行かなくていいの?」
どこかはわすれたけれど、片瀬くんも運動部だったはずだ。たいていの運動部は練習試合をどちらかの日程で入れている。時期的に三年の引退試合になる部活もあれば、新チームでの初戦になる部活もある。たいていが前者だ。
「行っても練習ばっかだし」
「そっか」
うなずきながら鞄から本を取り出す。図書館で見つけた、分厚さが取り柄の児童文学だ。ストーリーは何度も読んでいるせいで、ほとんど覚えている。
「……このシチュエーションで、本読み始めるかなぁ」
「なんか、悪い?」
「いや」
片瀬くんは鞄を持ち上げ、じゃ、と短く挨拶をした。
「なぁ」
「ん?」
「支倉が、参加するようになったの、誰のおかげだと思う?」
「……さぁ?」
「冴島だよ」
わけが、わからない。
「支倉が冴島捕まえてるとこ、みたんだ。やりとりは聞こえなかったけど」
――しかしお前も、都合のいい解釈で勝手に自己満してるやつに振り回されて大変だよな
「別に確信はないけど、あのあと、支倉すげぇ機嫌よくなったから」
片瀬くんが言っていることは、片瀬くんが観た現実であって、私がみたものではないけれど、少し目をつぶれば、浮かぶような気がした。
あれでいて、やさしいところもある。あまりはっきりとは、みえるところではないけれども。
「そっか」
素っ気ないふりの返しに興味を失ったのか、片瀬くんは足早にクラブへと向かった。入れ違えるように、話題に上がった人物が、どう言った風の吹き回しなのか突然、現れた。
すこし、憔悴している風で。
「冴島、何かあったの?」
そもそも部活に所属していない冴島に限って、文化祭のこの時期になにがあるとは思えないが、なんだか今の風体が、自分の知る彼とはかけ離れていて気にかかった。
さっきの話を聞いたせいか、強い気持ちで思った。
――冴島の助けになりたい。
「おなか空いたとか? 帰宅部は、図書室が控え室になってるよ? 屋上も開放していないから、行っても大丈夫のはずだよ?」
「屋上、か。お前は……平気だったんだけどなぁ」
いつの間にか見上げるようになった背丈を、彼の顔を、じっと見つめる。憔悴しているのではなくて、伸びた髪が顔に陰を与えているだけだと気づいてほっとした瞬間、目の前の顔が廊下の天井に変わった。
抱きしめられている感覚に気づいたとき、鼻孔には汗のにおいがした。伝わる体温がとてもあつくて、肌越しに伝わる鼓動は速い。身体がきしみそうな力の加減に悲鳴を上げそうになって、冴島のつぶやきにそれはこらえた。
「二人だけの場所だったんだ。お前がいても根っこの部分は変わらなくて、だから、あそこだけは」
いつかの光景がよみがえった。
李花先輩が、高崎先輩と一緒に屋上にいたあの光景。
私は、真理先輩に彼氏ができたことに驚いた。――でも、冴島は、私が想像していたよりもずっと、ずっと……傷ついて、いるんだろう。
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第2部 第7話