サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
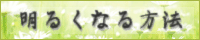
第2部 第1話
いつも通りにバスに乗って、授業についての話をしていたと思う。笹本くんの方が先に降りるので、たぶん、「そろそろだね」ぐらいのことは言ったはず。いやもう、その後起きた事件のすさまじさに、脳みそがすでにバグを起こしている。記憶があやふや。
「青木さんのこと、好きなんだ」
だから今思い出すと、この一言だけしか思い浮かばない。
あまりの突然さに頭は混乱、黙り込んでしまった。けれども笹本くんはバスを降りるときには、なにもなかったように「また明日」なんていうものだから、その瞬間、告白を「なかったこと」に変換した。
そうした数分後には、「返事は待ちます」っていうメールを私の携帯が受信して、再びおそわれた現実におののいた。
告白なんて、思いもしなかった。しかも笹本くん。
二年生で同じクラスになったものの、文化祭実行委員と生徒会役員という接点からよく話すようになったものの、多少ご厄介になったために他の人よりも接点が増えたものの、同じ塾に通っているから自然と会話は増えていったものの、――自分が誰かのそういう対象になるなんて。
そもそも自分に、恋愛対象なんていないし! どうしたらいいのか!
ぐるぐる頭を巡る思考は無限ループを繰り返し、ふと笹本くんの「また明日」という言葉をリフレインする。明日どんな顔をしてあったらいいのかわからない、なんて少女漫画みたいな思考回路が自分にあるとは思わなかったんだよこの時まで。
手紙は途中のまま、引き出しにしまう。やっぱりだめだった。なんだかこう、落ち着かせるためにいいかな? と思ったけれど、逆にスイッチが入ってどうにも収拾がつかない。困った。
これは本来の一般的女子ならば、顔を赤らめて思うことじゃないかな? 成績優秀、スポーツ万能で生徒会もやっているようなクラスメイトのあこがれ男子からの告白なんて! ……いやいや、そもそも告白されたことが非現実的だから困っているわけで。あれやこれやと思いながらも、顔面蒼白で明日をイメージトレーニングする。
朝の段階ですでに、一緒のバスに乗ることになるんだよなぁ。お昼は一緒。帰りも一緒。友達少ないせいなんですけどね、これ。
考えあぐねた結果は、案の定無難なところに落ち着く。
一緒のバスに乗れるはずはないので、始発に乗って塾に行きましょう。
それなのに。
帰り、笹本くんが先に降りると言うことは、行きは私が先に乗っている。
いつもと同じ、一番後ろの席に座るんじゃなかったと後悔しながら、私を見つけた笹本くんは当然のごとく隣に座り、当然のごとくこちらに顔を向ける。私は、目線をあわせないよう、懸命に運転手さんの方向を見続けた。
そして、懸命に祈る。はやく、はやく、目的地についてほしい、と。そんな都合のいいことはなく、いつも通りに駅まで十五分はかかるんだけど
「青木さんって、意外に、やることが極端なんだよね。選挙で啖呵切ったり、そもそも、屋上に通い続けたり。かと思ったら、優等生面で何もしない。じゃぁ僕を避ける為に青木さんがすることって何だろうと思ったら、まずこれが先に浮かんだんだよね」
全くもってその通りだ。塾は変えられないし、成績がよすぎるせいで見合ったクラスは一つしかなく、代替日程も組めないなんて不公平すぎる。
お弁当は外食にすれば何とか避けられるだろうと思ったのに、笹本くんも見事にお弁当箱をもってきていない。こっちは母親に不審がられながらも、お小遣いを切り詰める覚悟でお弁当を辞めたのに。
「返事は待ちますってメールしたけど、たぶん、この分だと一生避けられかねないから。『なかったこと』にしてもいいよ。でも、」
間があった。気になって、ふりむいてしまうと、目線があった。
ああ、罠にハマッタ気分だ。
「恋愛対象として、僕をみて? きっと、悪いやつじゃないと思うんだ」
――結局、その日のお昼は一緒に食べて、帰りも一緒に帰った。
家について夏期講習の復習をしながら、行きのバスでの、笹本くんの発言を思い出す。帰りはファーストフードで籠城し、なんとか一緒にならないようにした。
どうにかなりそうだ、本当に。
悪いやつじゃない、もなにも……委員会ではかなりお世話になっている。生徒会選挙の時も、緊張でがちがちだった私に声をかけてくれた。サッカー部に所属するさわやか少年のイメージそのままで、「いい人」だと思っていた。
だから、常に別次元の人だと思っていた。
夏期講習中、お弁当を一緒に食べていて楽しかったし、ささやかな気遣いをしてくれているあたり、同級生の女の子にもてるのも実感していた。ただそれはどこかで、壁に仕切られた向こう側にある世界を、ちょっとした偶然で体験しているような感覚だった。
私とはまったく違う世界に住む生き物ぐらいに思っていた。なのに、笹本くんは違っていたのか。
ずっとこの距離を保って行くんだと思っていた。笹本くんと話していると頬を紅潮させる、そんな女の子が彼女になるんだろうと、同じ教室にいながら思っていた。それは間違っても、私じゃなかった。
告白をされた時点で、壁は破られた。でもそれを、笹本くんは『なかったこと』にしてもいいという。でも、事実は事実だ。告白を一時的に「なかった」ことにできるかもしれない。けれど、その期限は誰にゆだねられているのだろう?
夏休みいっぱい? 文化祭まで? 冬休みまで? ……私と笹本くん、どっちがどうなれば、解決するんだろうか。
笹本くんを好きになる可能性が、どこにあるんだろう?
二学期が始まった。
お昼のチャイムを校内で聞いているのは、ほんのわずか。始業式と大掃除だけの今日は、十一時も過ぎると、帰宅部の生徒はほとんどがいなくなっていた。
午後から委員会のある私は、屋上で一人、お弁当を広げていた。こういうとき、真理先輩からもらっている屋上の鍵が活躍する。基本的には真理先輩か冴島のどちらかが開けているんだけれども、今日は二人ともすでに帰ったのか、屋上はがらんとしていた。
むき出しのコンクリートに座って柵に身体を預け、屋上の空をぼーっと眺める。雲の流れが速い。箸が進まない。
笹本くんとは、すでに会ってる。でも、なにもない。
これから委員会で会う。それが気持ちを暗くさせる。
「――か、りー、か?」
「え、」
真理先輩だろうと見当はすぐについた。帰ったのかと思ったのに。声のするドアへと視線を向けると、目の前の人物が遠目には「それ」とは思えなくて、私は言葉を詰まらせた。
首筋をさらけ出したショートカット。色も、茶でなくて黒い。長かったはずのスカートからは、風で膝小僧が見え隠れする。どこからみても健康的な女子中学生だ。それも、私より年下に見える。
「えっ、イメチェンですか?!」
「そんなに?」
真理先輩は笑いながら隣に腰を下ろし、白い素足をコンクリートの上に伸ばした。うう、なんだこのキレイな足は。学校指定の白のハイソックスをはいているのに、膨張しているようになんて全く見えない。
小さな二段のお弁当を広げ、両手を合わせていただきます。いたって一般的な行為に、何ともいえないぎこちなさを感じる。いや、動作自体にはなれた感じがあるから、ぎこちない……とは言わないか。
違和感?
「なにか、あったんですか?」
一学期末、真理先輩には何かが起きたらしいことは、端から見ていても明らかだった。委員会で屋上に来る回数は激減したけれども、あれだけセンセーションに……学期末の試験結果が出れば、だれだって何かが起きたことはわかる。
ただ寂しいことに、何かの正体を、私は、知らない。
「そう、感じる?」
先輩が、少女のようにほほえんだ。自分も少女って言う年齢だろうけど、真理先輩はなんというかこう、可憐な感じ。可憐なんて形容、前なら絶対使わない。
「私の知っている真理先輩じゃないみたい」
くす、と口元を押さえて笑う姿が、以前とは重ならない。もっとこう、前は口を大きく開けて笑っていた。真理先輩が、こういう笑い方をするところなんて、初めて見る。いや? と小首をかしげる仕草さえも絵になる、清楚な雰囲気の美少女だとは、知らなかった。
「いやじゃない、です」
「ありがとう。李花も、いつもと違う。なにかあった? 冴島と」
そこでどうして冴島があがるのかと言えば、まぁ私の交友関係の狭さに由来するんだろう。もしこの原因が冴島だったら、真っ先に真理先輩に相談しているんだけどな。
「冴島じゃ、ナイです」
「でも、誰かと何かあったのは確実かぁー」
先輩の鋭さと自分の言い方、どっちに軍配なんだこの場合。
「夏だもんねー。じゅうよんさいの夏! なにがあったかなんて、野暮なことはお姉さん聞かないよー」
むしろ聞いてほしい。ここで素直に言えたらいいのにと思っても、ぐるぐると渦巻く言葉を声にできない。真理先輩の顔をじっと見つめながら、進まない箸を置いた。
ぎゅっと手を握っても、話す勇気がない。
つまっていると、真理先輩がぽんと頭に手を置いた。
「李花は一人で抱え込むのに、一人で解決しちゃうから。――もっともっと、あたしは李花を、心配したいなぁって、思うよ」
「……?」
「あのとき相談してくれたことはどうなったんだろうとか、アドバイスには意味があったんだろうかとか……そんな心配を、李花にしたいよ。冴島がわかりやすいほど態度に表してくれるのに、李花は全くわからないから」
笹本くんの言葉がよみがえる。――優等生面でなにもしない。
そう、私は、なにもできない。他人からの評価とか、思われ方とか、それをとても気にして、こんなに心配してくれる人にすら悩みを話せない。
「ごめ、」
言えばいい。わかっているのに言えない。さらけだす、その行為にひどくおびえる。だから踏み込もうとしない。
なにも言わず、真理先輩が優しく頭をなでてくれる。それが苦しい。言ってほしいのに。責めるように言ってもいいのに。言わない優しさをずっと抱えてくれていて、それに私は甘えている。
笹本くんが何も言わないから。そんな優しさにあぐらをかいて、応えない。私は他人に優等生面をしながら、なんて不誠実なんだろう。なのになんで、他人はこんなにも優しいんだろう。
「ごめんなさい……」
自然と涙がこぼれた。自分が恥ずかしい。
隣にいる他人が、とても優しい。私は他人に対して、踏み込むことができないのに、どうしてこんなにもたやすく、包み込んでくれるのだろう。
――きっともう、一人で泣くことなんてできなくなる。
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第2部 第1話