サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
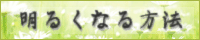
第10話
部活の子しか残っていない放課後。職員室のある二階は、時折職員室からの声が漏れるだけで、人通りはほとんどなかった。二階のすみにある、委員会が使う会議室の掃除ロッカーを閉めると、がたがたとわずかに音を立てたあと、静まる。
静まった部屋に、横開きの出入り口が開く音があふれる。私は動じなかった。ドアの窓から見えていたのだ、入ってくる人は分かっていた。
「名取先生、お久しぶりです」
先日配られた数学の点数は満点。学年の一割も取れなかった応用問題だって満点だ。こんな問題出すほうが悪い、といえるほど難しかったけれど、それを解くのが私の意地で、私らしさだった気がする。
ロッカーの近くで耳を澄ませば聞こえただろう機械音に、けれども名取は気づかなかったらしい。ロッカーから遠いのだから、当たり前といえばそうだけれど。
「きちんとご挨拶をしたことがありませんでしたね。青木李花です、名取和也さん」
「よく知っていたな、下の名前を」
「ええそれは。あなたと親しくしている女生徒たちとお昼を一緒に食べれば、二日に一回は出る名前でしたから」
「そうか。生徒の話題になるようになって、教師は一人前だからな」
「そうですか?」
「そうだよ」
腕時計を見た。十三時十六分。八十分テープに、がんばってもらおう。
その動作を、先生が目に留めた。
「その腕時計、いいね」
「これ、ぜんまい式なんですよ。母から少し、借りているんです」
かなりのうそだ。棚の奥にしまって出していなかった、母のものだ。譲るよ、という話もなにもない。ここ数日の間、引っ張り出して使い続けている。気づいたときにぜんまいをまわして、止まらないようにするのは面倒だが、数日つけていると、それもなかなかに愛嬌があっていいことに気づいた。
本格的に譲ってもらおうかな、と思わなかったことは、無きにしも非ずだが、この時計のルーツを考えれば遠慮せざるを得ないな。
「借りている?」
「というか、しまったまま出さない母の代わりに、使ってあげているんです」
「へぇ……」
ビンゴ。わずかに表情が変わった。母がタンスにしまった時期からして、プレゼントにもらったものだと思ったんだよね。律儀な人だから。そういったところがまたもてるわけだけど。
「我が家、母子家庭なんです。知っているでしょう?」
「まぁ、家庭報告書に書いてあるから……」
「そう。うちの両親、なんで離婚したんだと思います? いつ、離婚したんだと思います?」
「さぁ、それは」
両手を挙げた。外国人のI don't knowと言った感じに。数学教師には似つかわしくない動作だ。確かに知らないだろう。両親の離婚の原因は、今考えれば、ホント、くだらなかった。
「……離婚した時、あたしには弟がいたんです。ヴァイオリンが大好きで、それが生きがいみたいな、二コ下の弟。大好きで、だから、あえないと、さみしいですよね――好きな人にあえないと、寂しい気持ち、先生なら分かりますよね?」
だんだん芝居がかってきた自分の声が、いつもと違って聞こえる。実際、違っていそうだ。
「先生もそうでしょう? お母さんにあえなくて、私が憎らしくなった?」
「なにを言っているんだ、青木」
「じゃぁ、別のところから言えばいいですか? 最近、私クラスから総スカンくらってるんです。それもある日突然。前兆もなにもなかった。先生はいつものように、同じ女生徒たちと話していた……先生でしょう? 私を無視するように、クラスの子に言ったのは」
「なにを言っているんだ青木。でも、そんなことが……」
あるなら、僕がどうにかしよう。とか何とか言いそうだ、コイツの教師面は。でも私はそんなことを鵜呑みにできるほど、善人じゃない。
「知っていたでしょう? あの演習問題のときから、先生はすべて、考えていたんじゃないの?」
先生に変化はない。だから怪しいんだと、内心で突っ込む。
「青木、落ち着いてくれ。俺は何もしていない」
「そうね、確かに何もしていない。きっと女生徒に頼んで、内心のことをほのめかせば、毎日お目当てがあるからまじめに学校来てる子達なんて、すぐに陥落するわ。そんな友達いらないけど」
「お前に、それ以外の友達がいるのか!?」
よく知ってるわね。大分前から観察されてたのかも。ほんとのことだけど、名誉既存で訴えるわよ。
「クラスメイトに友達の一人二人、いちゃいけないですか?」
「はっ、いないから、あんな生徒と一緒に昼飯を食べていたんだろう? 青木。先生は常々、お前のことを心配して……」
「あんな生徒? ……よく言えるわね、自分の生徒に」
「言ってやるさ! 毎日毎日アホみたいな質問して、挙句の果てには名前で呼ぶんだぞ!? ウザイと思わない人間がいるか!?」
激しくののしったあと、顔色を変えてこちらに振り向く。
「だから青木、君はいつまでも……」
先生が私の肩をつかんだ。離れようとするけれどもびくともしない。瞬間的な恐怖を振り払って、にらむ。胸を張って顔を上げる。それが私だ。
「本当に、君は君の母親によく似た顔をしているよ。目を見張るほどの美人でもないのに、隙がなくて、凛とした姿に、自然と視線を奪われてしまう……母親のほうはくどくとすぐになびいたけどね、娘はさっぱりだ」
動かない私に調子付いたのか、片方の手をかたからセーラー服のタイに伸ばした。嫌悪感をこらえて、じっとしておく。
「お生憎様。これ以上手を出したら、痛い目見るのはそっちよ? 教育委員会が待ってるんじゃないの?」
「うちの父親と取引している会社の縁者が、うちの県の教育委員会にもいてね……そのコネで、教師になったんだ。それに君だって、傷ものになったあとに、そのことを訴えるのは恥ずかしいだろう? いやだろう?」
セーラーのタイを名取が抜き取った。嫌悪感が一気になくなったので、笑みを浮かべて足を上げようとした。瞬間、私の一メートルほど後ろにあったロッカーから、攻撃が始まった。
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第10話