サイトトップ>『明るくなる方法』目次>
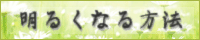
第4話
何だってついてないんだろう。
時計の長針と短針はまっすぐ上下に。短針が下、長針が上。外角も内角もないほど、きっちり百八十度で、それを記念しているのか、学校のチャイムまでなった。午後六時。
外は本降り。大雨。雨が地面に振り落とされる音が、やたら耳にさわる。服にしみこんだ湿気が、はだと服をくっつけようとする。夏ほどではなくても、不快指数は上昇中だ。
貸し出し用の傘は、返却率の低さのためにもうないといわれてしまったし、折りたたみの傘をかばんの中に常備できる私じゃない。かばんが重いんだよ。……ロッカーに入れてあると思ったんだけどなぁ。誰かに貸したんだっけ、アレ。
学校から家まで徒歩三十分。かばんでなんとかしのいでも、苦しい時間だ。バスに乗れればいいけれど、バス停まで歩いて三分。バスは十分から二十分間隔。今の時間は、ラッシュだけれど、すぐに来なかったら、と思うと大きな賭けだ。
おまけに今は冬服。雨に濡れたらクリーニング行きなのに、週のど真ん中ですぐには出せない。スカートのプリーツが取れないか心配だ。かけなおしてもらうとなると、ちょっと追加料金が怖いぞ。
じっと雨を見つめていても、やまないものはやまない。かれこれ三十分以上、二時間未満が過ぎていた。少しぐらい雨足が弱まってもいいと思うんだけど、そんな気配はまるでなし。日ごろの行いはいいはずなんだけどなぁ。
図書室は、こんな日に限って館内整理日だった。うっかり忘れてたよ。いつもなら七時までやっているのになぁ。学校の生徒は五時過ぎた頃から、帰宅催促があるんだけどね。
いつものように、お母さんのお帰りは遅いはず。うーん、七時ぐらいまで待てば、バスを使う先生の傘に入れてもらって……
「おい、そこの優等生」
優等生の言い方がなんとなくイヤミっぽい、この声は。
「なによ夢助」
「……夢助ってずいぶん古い言葉だなぁオイ」
他人の語彙力に文句をつけるな。意味分かってるのか? コイツ。
今日の昼のワイドショーを独占した男、冴島秋。辺りを見回して、誰もいないのを確認するのが癖になってしまう、イノウエマリの同格だ。
「俺的にはどうでもいい人間その一なんだが、真理は同類に随分同情的だからな」
だれが同類と吐き捨てて、雨を見つめながら、用件の分からない男の話を聞いている私は、ずいぶんとこっけいに後ろのドアガラスに映るに違いない。
「何かあったら助けてやれといわれたもんでな。数学のときもやる気はなかったが、お前、あの教師嫌いだろう? 俺もだが」
「アンタに言われることはない!」
顔に向かって一気に、血が顔をめぐる。顔がほてっていくのがよく分かった。
この男のせいだ。何で分かるの? 図星だ。自信があったのに、自分の優等生面には。
なんかいけ好かないんだ、あの数学教師、名取。
「認めておけ。しょせん優等生も化けの皮だからな。ほら」
放物線を描いて、棒状のものが私の手に収まる。折り畳み傘。……よく見ると、ロッカーにあったはずのものだ。若干ほこりもかぶってるが、それはカバーだけの話。
なぜこの男が? こいつ自身が盗ったわけじゃないだろう。だって、私のロッカーの鍵番号は、宿題とかのノートの貸し出しが面倒なときに、教えているだけ。知っている子は限られている。否、五人以下。
私は唇をかんだ。まだ序の口だ。
「優秀な優等生様のことだ、予想はついてるだろうよ。ちなみに無駄なことは考えないほうがいい。本当に無駄だから」
無言で折りたたみの傘を広げる。器物破損をするほどは憎まれていないらしい。無傷の傘をさして、生徒玄関から数歩歩いた。若干のためらいの末、振り返る。
「ありがとう、……冴島」
「しょっぱなから呼び捨てかー、……青木だっけ?」
呼ばれた苗字は、もう人生の半分、使われたもの。あとすこしで、その半分を超えてしまう。そうしたら私は全部、あの頃を捨てなきゃ行けない気がしてしまった。もう戻れない過去。戻れない、姓。
「名前で良いよ。優等生だって構わない。あんま好きじゃないんだ、苗字」
「――なら、真理と一緒だ」
生徒玄関の前で微笑む冴島。若干の遠目でよくは見えなくても、憂いを含んだその笑みは、やつをワイドショーのように取り上げていたオンナノコが見ていたらもしかしたら、卒倒ものだったかもしれない。
母性本能をくすぐられるというか……? 私も例外じゃないみたいだ。
冴島の笑みと、イノウエマリの苗字嫌い。おびえながらだった好奇心が少しだけ、違う形を見せ始めた十月末。十一月の学期末まで、あと三週間。
サイトトップ>『明るくなる方法』目次>第4話