サイトトップ>『うた秘め』目次>
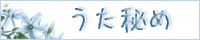
第3章 孤独のみらい 2
←前|,a href="./26.html">次→
空に広がる天気は、快晴。小さな丸窓から差し込む光にリリアは眉をひそめ、船で一番キレイだとセイが胸を張っていた毛布を頭からかぶり直した。寝台にしかれたマットはやや硬いが、ないよりましだ。そもそもこの船上では、ない方が当たり前なのだし。
「まだ……寝る……」
誰も聞いていないだろうなと寝ぼけた頭で思いながら、口を動かした。だが思惑はそれて、近くで聞いていたアルタルフが毛布に顔を近づけた。
もぞもぞと動きながらも、全身を毛布ですっぽり包んだリリアは、大陸で見かけた芋虫のようだとあきれつつ、アルタルフは思案顔で、毛布を見つめた。
毛布からは再び寝息が聞こえ始め、それをかき消すように外で船乗りたちが朝のかけ声を叫んでいる。一から順々に番号を行っていく人数確認。今日の持ち場の確認。サイガからナンチョウに行くような、距離の短い航行ではない。乗っている船夫全体の七割で基本的な航行。残り三割は緊急時にのみ働き、何もなければ休みだ。
そうして、全員が無事に目的地につけるよう、また、疲れをためない仕組みになっている。
それを初めて聞いたときのリリアはさらに根掘り葉掘り聞いていたようだが、彼女が満足するよりも船夫が持ち場に戻って働き始める方が早かった。
船に乗ってからのリリアは、始終そんな感じで暇をもてあそんでいる。初日こそ船酔いで床からあがれなかったものの、三日目には甲板を歩き始め、五日目には船員への質問攻めを開始した。適応能力が高いのか低いのか、アルタルフにはわかりかねるが。
それでも人と話し続けるリリアは、アルタルフにとって異質な存在だ。
彼女自身は知らなかったとはいえ、自らの死を条件に彼女に旅の同行を許したものの、彼女が歌う気配は一切ない。自分の歌で誰かが死ぬと鳴れば二の足を踏むのも当然かも知れないと、当たり前のことに思い至ったのは、彼女に指摘されてからだ。
アルタルフ自身は、彼が生きる価値はないと思っている。彼の存在がサイガを苦しめ、島に災いをもたらしている。そんなこと、亡き父が知ったらどんな顔をしただろうか。――もっとも、調べる術はないが。
母も父も、すでにない。それは自然の道理だが、甥や姪までいなくなると、すこし苦しくなる。実年齢からすれば、リリアぐらいの孫がいたっておかしくない。そんな年齢まで、身体の時間を止めたまま生きている。
そんな自分がこれ以上生きる。無理だ。
だから一日でも早く、死にたいと思う。
そのためには、アルタルフをこの身体にした活きの原詩同様の力を持つ、滅びの原詩が必要だ。どちらも口承で伝わり、文字にはなっていない。活きの民、滅びの民の中でも選ばれた血筋で、成人した者のみが教えられる。――そして滅びの民はすでに、離散している。
リリアは滅びの民の生き残りだ。彼女が唯一の生き残りであるとすれば、原詩はすでに失われた可能性が高い。もしそうなったら、彼女の歌で徐々に、この身を削ってもらうしか術はない。たとえ十年かかろうと二十年かかろうと、歌によって得たこの不死身の身体は、歌によってしか死ぬことができない。
そのためにも、毎日でも歌を浴びたかったのに。
歌うことは拒絶された。
アルタルフは、自らの歌を口ずさんだ。――美しの歌とかつて父から送られた号を、思いながら、顔に触れる。頭に人の顔を思い浮かべ、顔の造作をかえるのが、この歌の特徴だ。あまり知れ渡った顔をしていないので、基本的には使わない歌だ。主な使途は人をからかうことぐらい。
リリアをからかうのに、数年ぶりぐらいに使った気がする。
「……リリア、そろそろ起きないと空腹でまた酔うぞ」
散らかった思考をおいて、アルタルフはリリアに声をかけた。いつの間にか船乗りたちの申し送りやら朝の挨拶やらが終わり、各自の持ち場で働き始めた。これ以上料理係を待たせるのは酷だ。
「りーりーあー」
おそらく耳のあたり、とおぼしき場所で声を荒立てても毛布の中から出てくる気配はない。なんて寝相か。
「これは、どうだ?」
ああ、セイになんて言われるか――そう思いながら、手で毛布をぎゅっとつかむ。場所はくの字型に曲がっているところの、少し上。丸まった背中とおぼしきところの、背中とは反対側。
「はっ、腹の肉をつまむなぁっ!!」
絶大なる効果でもって、リリアを目覚めさせた。
サイトトップ>『うた秘め』目次>第3章 孤独のみらい 2